ひとひら・・・ひとひら・・・
頬を掠め舞い落ちる、その―――。
艶やかなまでの・・薄紅の花弁。
たとえるならそれはあなたと僕の・・。
『恋』そのもの。
風に靡くその漆黒の髪に惹かれなければ・・・あなたと僕は今ここにこうして一緒にいる事はなかっただろう。
全ては桜に魅せられた幻ゆえに―――。
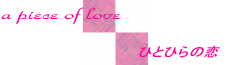
少しだけさり気なく開けられた窓から緩やかな風が流れ込む中・・。
「そろそろ・・・お茶にしようか」
彼の一言で僕の作業は中断される。
室内の右端の一角に配されている小さなキッチンへ向かうと、
「今日は少し爽やかな演出を愉しみたいね」
聞こえてきた彼の言葉に沿うように、準備を始める。
お湯を沸かす間に、備え付けられた真っ白なキャビネットからガラスポットを取り出し
いくつか取り揃えてあるティーカップの中から、ティーポットと同じガラス製のものを選ぶと、
沸騰したお湯をティーポットとティーカップの両方に注ぐ。
彼の為に、美味しいお茶を入れる努力を怠った事はない。
それは果たして自負できる事なのかどうか・・。
暫し考え込むように視線を巡らせ・・温まったポットとカップを確認した僕は、お湯を捨てると、
キャビネットの更に奥からとっておきのドライハーブを取り出した。
彼の望む演出の為に。
取り出されたとっておきのそのハーブの名は、マロウ。
ビタミン豊富なこのハーブはリラックス効果も抜群だが、それ以外にもちょっとした不思議が隠されている。
別名『サプライズティー』とも呼ばれているこのハーブ。
僕は、ポットに適量マロウと紅茶の葉を入れるとその上から再び沸騰したお湯を注いだ。
徐々に広がるブルー・・。
マロウから溶け出した薄青色がやがて濃い、けれど透明な藍になるのを見計らって
僕は用意したティーセットを彼の元へと持っていく。
「へぇ・・きれいな色だね」
僕の手元のガラスポットを見るなり、彼はそう言った。
「涼しげな感じで、とてもいいね」
満足げな様子に、僕も口元を綻ばせる。
けれど・・これで終わりではない。お楽しみはこれからなのだ。
「気に入ってもらえて嬉しいです」
僕はお座成りな言葉を返しながら、彼と僕のティーカップにハーブティーを注ぐ。
ポットと同じ色彩がカップに広がる様を、彼は頬杖を附きながらじっと見つめる。
「どうぞ」
カップに注ぎ終わった僕は、彼の前にそれを差し出した。
「ありがとう」
差し出されたカップを受け取った彼は、香りを愉しむようにその整った鼻梁に近づける。
「いい香りだね・・・好きだよ、こういうの」
椅子に座ったままの彼は、隣に立つ僕をチラリと上目遣いで見上げた。
そんなちょっとした仕草で、僕がどれだけドキリとしているか・・・この人は本当に分かっているのだろうか?
時々・・・
僕は、ワカラナクナル。
「ああ・・香りもいいけど、くせのないあっさりとした味もいいね」
彼の言葉に、僕は緩く微笑みを返し、暫しハーブティーと戯れる彼を見つめる。
『彼の唇に触れるそのティーカップが僕であったなら』 と・・。
そう思っている事は決して口には出さない。
けれど・・・。
時々、彼は気づいているのではないかと、思う事もある。
彼の悩ましげな仕種は、僕を誘っているとしか思えないから――。
ゆっくりと流れていく午後の一時。
窓の隙間から風に乗って桜の花びらが一片、彼のカップに舞い落ちる。
不意に浮かんだその薄ピンクの訪問者に、彼はそっと微笑みを浮かべた。
「可憐だね・・・一片、というそのいじらしさがまた魅力的だ」
花びらを細い指先で弄びながら、彼は言う。
少し冷めてしまった紅茶に、僕は暖かいハーブティーを注ぎ足した。
花びらはまだ浮いたまま、くるくると彼のカップの中で踊っている。
その様子を眺めながら、
「薄いピンクもいいですけど・・・」
僕は徐にあるものを取り出した。
「鮮やかなピンクもいいと思いませんか?」
「鮮やかなピンク・・?」
僕の言葉を反芻し問いかける彼の目の前で、僕は用意しておいたもう一つのもの・・
レモンを彼のカップに入れた。
「・・・・えっ!?」
その途端、
ハーブティーの色が藍からピンクに移り変わる様を見て、彼は驚愕に目を見開いた。
滅多に見れないその表情に僕は少しだけ得をした気分になる。
一瞬の至福。
彼のこんな表情を見れるのはきっと自分だけだろう・・。
そして、そんな些細な事で高揚する胸の内を、彼はきっと知らない。
いや、知らなくていいと思う。今は、まだ・・・。
「爽やかな演出にちょっとした驚きをプラスしてみたのですが・・・いかがですか?」
次第に藍とピンクのマーブル模様な色合いが鮮やかなピンクに移り変わる中、
じっと飽きもせずにその様子を眺める彼に僕は問う。
「レモンを入れただけでこうも色が変わるなんて、相変わらず・・・」
彼はそこで一旦言葉を切り、一つ溜め息を吐くと、
「キミには驚かされるね」
僕を見上げて極上の笑みを浮かべた。
あまりにも綺麗で艶やかで・・・それは見るものを魅了して止まない、
彼だけに許された微笑。
そして・・・。
その微笑をこんなにも間近で見る事ができる喜びは
僕だけに許された特権。
入学式のあの日――。
風に靡く彼の漆黒の髪に惹かれた僕は、そっと彼の後を追った。
もうすぐ式が始まるという差し迫った時間にも関わらず、
彼は桜の木の下に一人佇んでいた。
透き通る白い肌。その頬を掠める程少し長めの艶やかな黒髪。
その姿があまりにも優美で・・。
強く吹き付ける一陣の風。桜吹雪のようにその風に舞う花弁。
その様が神秘的にさえ思えて・・。
僕は微動だにできず、ただじっと彼を見つめていた。
不意に、式の始まりを告げるチャイムが放送と共に鳴り響く。
彼と僕の間にあった静寂がその音に破られる。
ふと振り返った彼は、
「行こう、式に遅れるよ」
そう言って、僕に向かって微笑んだ。
舞い散る鮮やかな桜よりも美しい・・・。
それは桜の見せた幻だったのか・・・?
今となっては、彼の微笑みが現実のものだったのかどうかは定かではない。
何故彼が知り合いでもない僕に声を掛けてくれたのかも・・。
けれど一つだけ確かな事がある。
それは・・その瞬間から、僕は誰よりも彼に一番近い場所に来たという事。
僕はその為の如何なる努力も惜しむ事はなかった。
今こうして彼の傍で彼の為だけにお茶を入れられるのも、そうした努力の賜物だといっても過言ではない。
彼の隣に立つにはもう少し時間が必要だけれど・・。
今は、まだ・・・。
この場所でもう少し彼の微笑みを見ていようと思う。
いつか、彼と同じ位置で同じものが見れるようになるその日まで・・。
そして、もしも
その時が来たら――。
ひとひら・・・ひとひら・・・
頬を掠め舞い落ちる、その―――。
艶やかなまでの薄紅の花弁よりも鮮やかな『恋』を・・・
あなたとしても、いいですか――?。
風に靡くその漆黒の髪に惹かれなければ・・・あなたと僕は今ここにこうして一緒にいる事はなかっただろう。
これが桜に魅せられた幻でない事を、僕は祈る―――。
